R7.6月18日(水)
療育手帳の再判定のためそう君と一緒に児童相談所のある総合福祉センターへ行って来ました。
療育手帳再交付手続きの流れ
療育手帳は、判定年月の2~3か月前に福祉センターから通知が来るので市役所で申請の手続きをします。(通知がない自治体もあるようです)
住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口に必要な書類一式を提出しその窓口で再判定の日にちを予約します。
申請受付後、窓口の方が県総合福祉センターに電話をかけ、判定日時の予約をして下さいました。我が家は候補日を数日上げてもらい都合の良い日時に予約してもらいました。
 そう君ママ
そう君ママ
手続きに必要なもの
1.顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景、1年以内に撮影したもの)
2.マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)
3.持っている手帳



再判定の日
当日、15:00の予約だったため学校を早退して会場へと向かいました。
そう君は、普段にないスケジュールの時に不安が強くなる傾向があるので朝の段階で『病院』のシンボル(聴診器)を使って本人にスケジュールを伝えておきました。
学校にお迎えに行き、車の中で聴診器を渡し会場へと向かいました。
車の中では、先生とお話しをする事、先生に質問される事などを口頭で説明。
施設内へ入ると第一関門のエレベーター。
お部屋は二階ということで、エレベーターが苦手なそう君は持参した安心グッズのタオルを噛みながら少し不快な声を出しつつ会場に到着。エレベーターは、閉塞感や浮くような感覚が苦手みたいです꜆꜄꜆
施設のエレベーターが小さく、リクライニングをギリギリまで起こしなんとか乗れました꜆꜄꜆そう君よりバギーが大きな方や呼吸器などでリクライニングが掛けれないお友達は乗るの無理じゃないかなってくらい小さくて大変でした꜆꜄꜆
古い建物だから仕方ないかもしれないけど、成人したらきっと乗れないんじゃないかな‥。
再判定の面談
面談の内容としては、私(母)への聞き取りが主で進みました。
・ご飯はどうやって食べていますか?
・ご飯の形態は?
・排泄は?
・排泄の際の意思表示は?
・コミュニケーションは?
など、基本的な日常生活動作や本人の様子について質問されました。
当日持参していたもの
・お薬手帳
・療育手帳
・身体障害者手帳
・安心グッズ
・サポートブック
当日個人的に持参していて良かったのはお薬手帳とサポートブック。
現在、1日10種類以上飲んでいるそう君。お薬手帳を見せるとメモを取られていました◡̈
お薬の飲み方も聞かれたので、写真つきでお伝えできたのも良かったです。
コミュニケーションへの質問は、ジェスチャーの写真をまとめた一覧のページをお見せしたら一発で理解してもらえました。
こういう時、サポートブックを作っておいて良かったなと思いますね◡̈
最後は物を使っての検査
黒いバックのような物から、先生が物を出して来られました。
はじめは鈴。
リンリンとそう君の前で鳴らされると、そう君はそれを取ってリンリン鳴らしてくれました(素晴らしい)
次は、コップと四角い木のブロック
「コップにブロックを入れてねっ」と声掛けされ、ブロックを持ちはしたものの遊び始めて入れる事が出来ずに終了
とこんな感じの流れでした。
面談終了後に質問
判定終了後、少し待つように言われ待機。
戻ってこられると「前回同様、重度:Aでの更新になると思います」
と担当の方に言われて終了
最後に質問ありますか?と言われたので、療育手帳の再判定は、どのような検査基準を用いて検査をされるのか疑問に思ったので質問してみました。
「○○式など、検査方法があると思うんですが、うちの子はどのような判定基準を用いられたんでしょうか?」
回答は
そういう判定方法では検査は難しいと判断し重心児者用の様式で検査したとの事でした。
面談時に判定用の用紙を持参された際、チラッと『重症心身障害児者用』という文字が目に入ったのでその子の状態に合わせて自治体で決まった様式があるのだと思います。
全国的に、療育手帳の判定は簡易的な検査で判定されるんですかね?
終始落ち着いていたそう君、安心グッズで穏やかに終える事ができました。
まとめ
判定は、30分程で終了。
成人を迎えるまで、定期的な更新が必要なのでその度に写真を撮影したり役所への手続きに行ったりと大変です。だけど、必要な福祉サービスを受けるためには大切な手続きになりますね♪
そう君のように重症心身障がい児(重度)さんは、特別児童扶養手当の更新の時などに手帳を持っていると医師の診断書が不要になったりと手続きが簡略化出来る場合もあるので助かります。
これからはじめての更新があるという方の参考になれば嬉しいです。
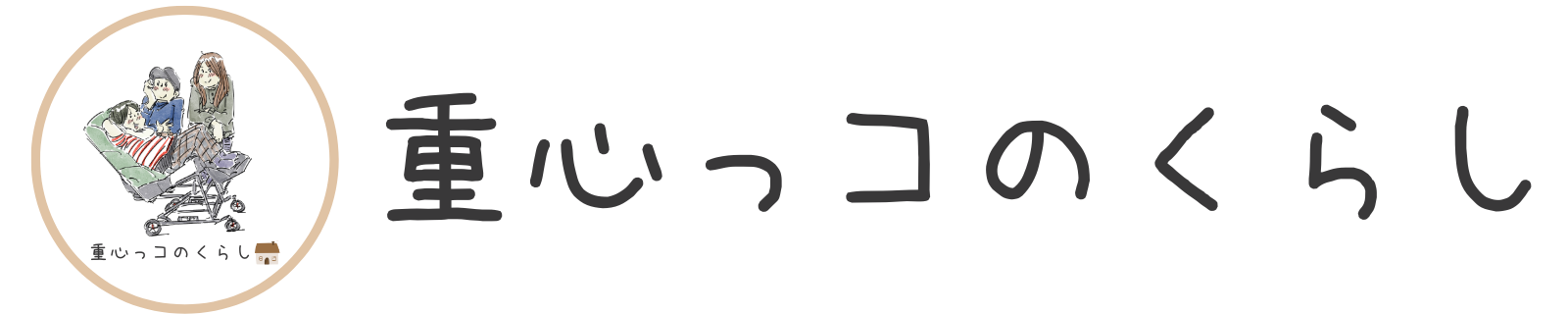







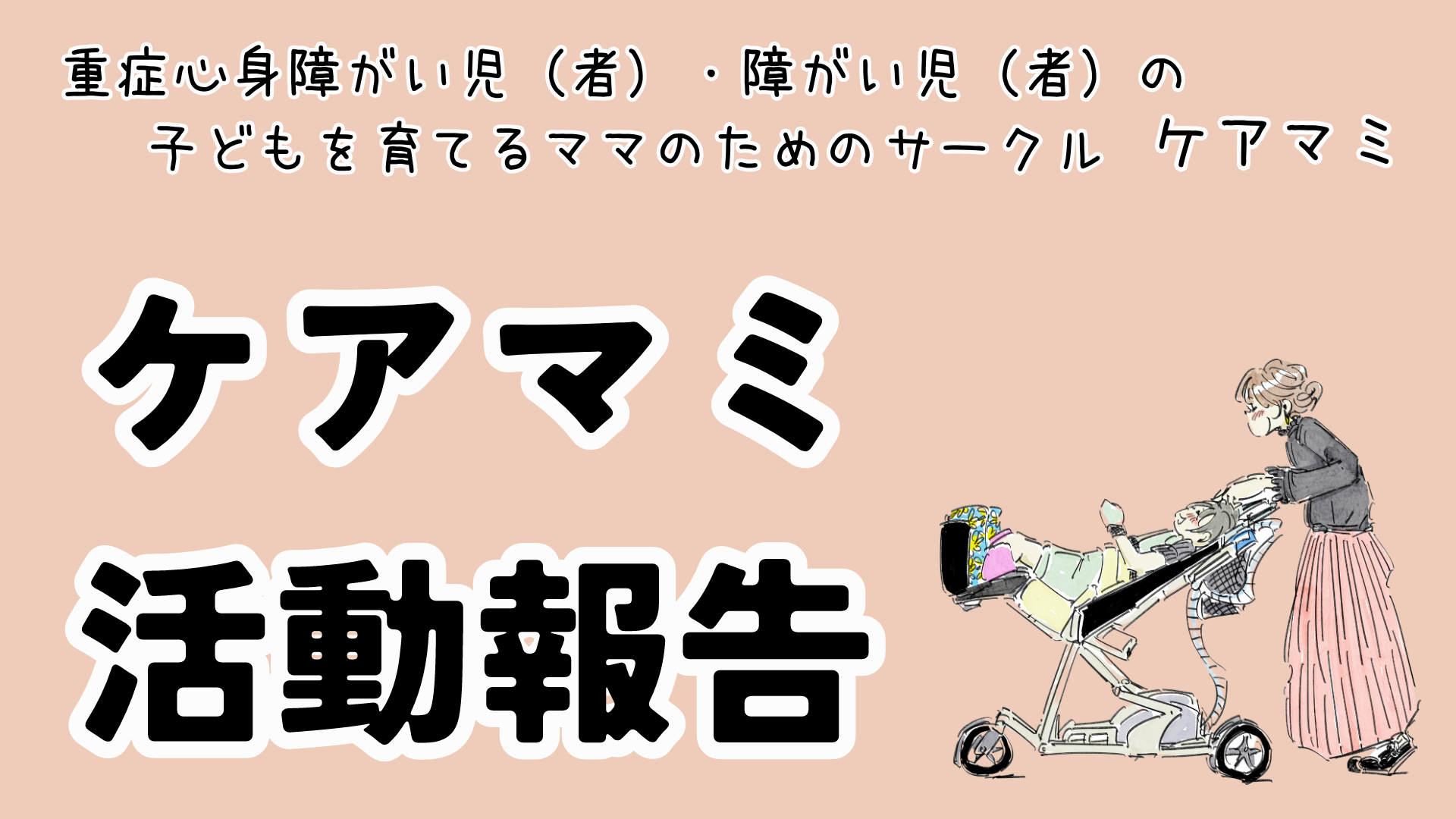



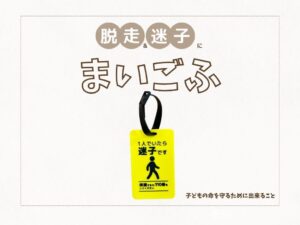

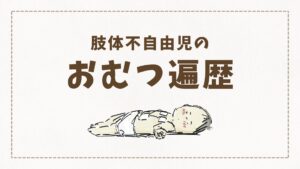




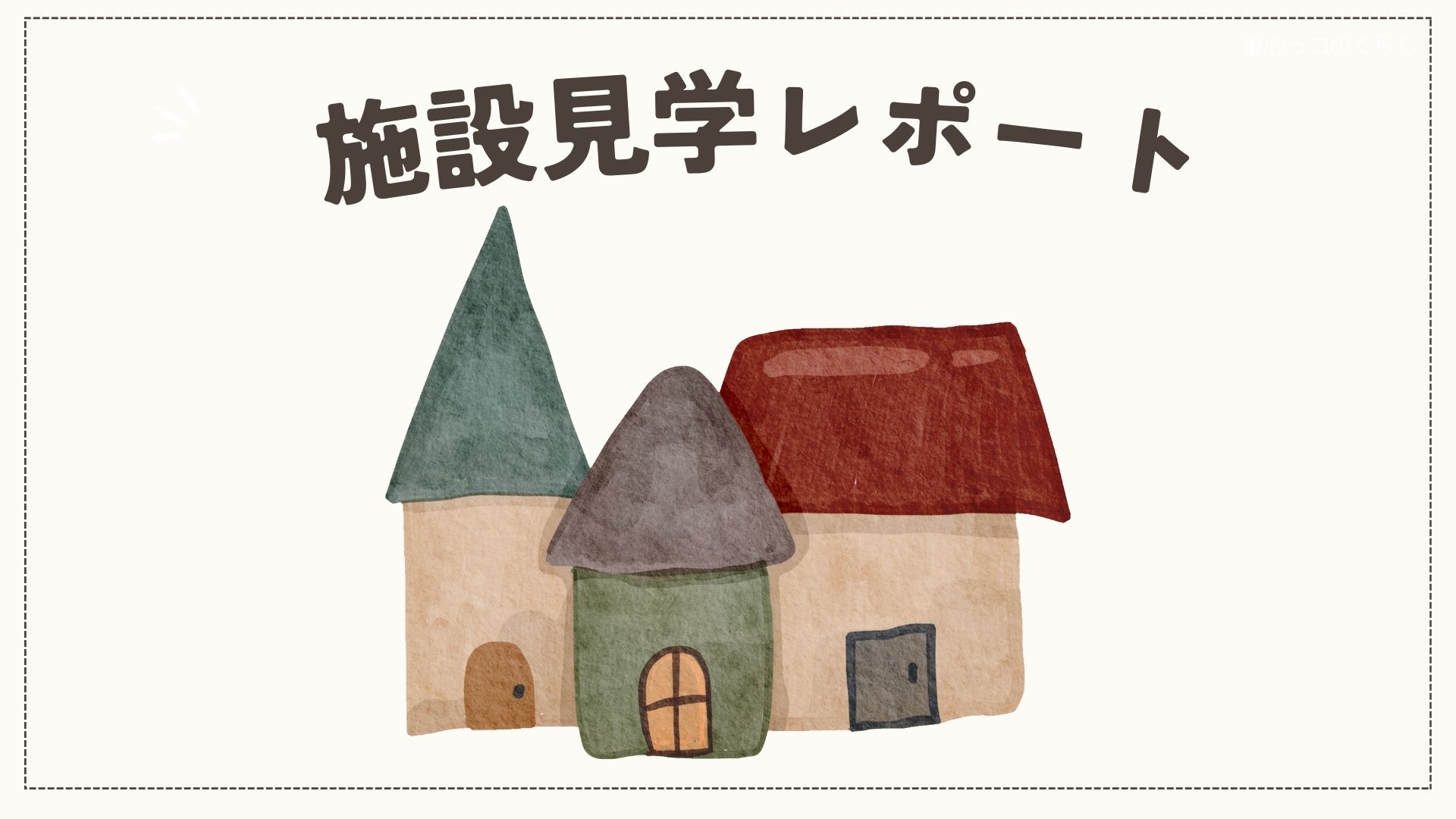

コメント